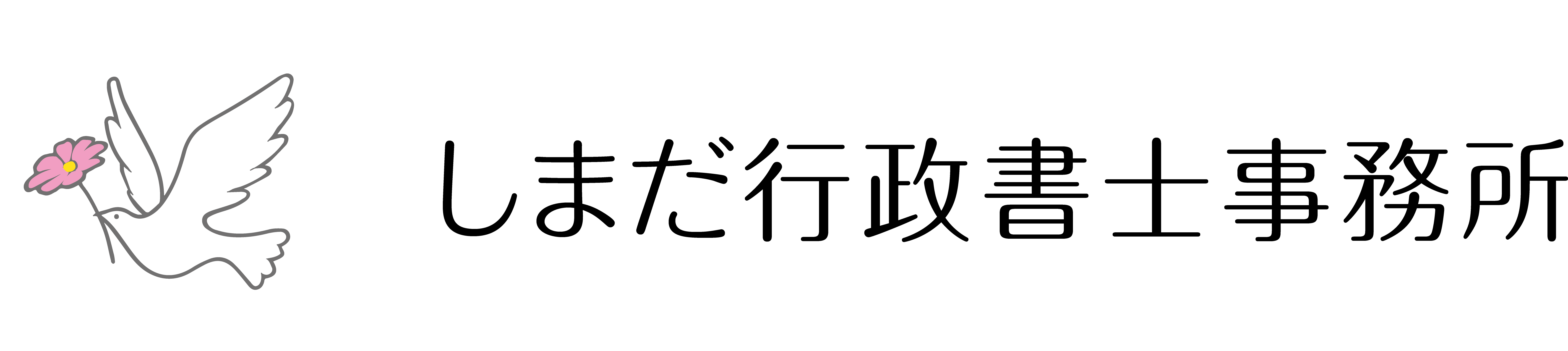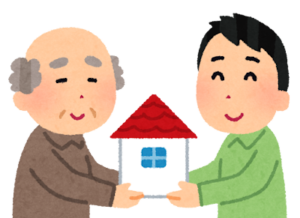特定技能【就労ビザ】
~人手不足を支える、新しい外国人就労制度~
目次
特定技能の必要性
まず、日本社会は少子高齢化が進み、働き手が年々不足しています。
特に、介護・建設・製造業・外食などの分野では、人材の確保が深刻な課題となっています。
そこで、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
特定技能とは?
特定技能とは、ある程度の専門性や技術を持つ外国人が、日本の産業分野で働けるようにするための在留資格です。
具体的には、2019年に制度がスタートし、外国人が16の特定産業分野で働くことを目的としています。
そのため、「留学」や「技能実習」とは異なり、本格的な労働力としての受け入れが可能になりました。
特定技能には2種類ある
ところで、特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。
まず、「特定技能1号」は、一定の技能と日本語能力がある人が対象です。また、受入れ機関又は登録支援機関による
支援の実施が求められていることに、注意が必要です。この資格では、最大5年間の在留が認められ、原則として家族の帯同はできません。
「特定技能2号」は、より高度な技能を持つ人が対象で、在留期間の上限がなく、家族も帯同可能です。
働ける産業分野が決まっている
ただし、特定技能はどんな仕事にも就けるわけではありません。
というのも、制度の目的が「人手不足解消」であるため、政府が定めた16の分野に限って就労が許されています。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造(素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
また、各分野ごとに業務区分がきまっており、それ以外の活動はみとめられません。同業種内であれば転職も可能ですが、変更申請必要になります。許可が出るまでは転職先で就労できないので、注意が必要です。
ビザ取得には試験が必要
では、誰でもすぐに取得できるのかというと、そうではありません。
特定技能1号を取得するには、分野ごとの技能評価試験に合格する必要があります。さらに、日本語能力もN4レベル以上が求められます。ただし、技能実習2号を良好に修了した人は、日本語試験が免除される特例もあります。
移行もしやすい制度
一方で、特定技能は「キャリアのステップ」としても設計されています。
つまり、技能実習を終えた人が特定技能へと移行したり、特定技能1号から2号へと進んだりすることが可能です。
このように、段階的な就労継続ができる点も制度の特徴です。
特定技能ビザ取得のための書類一覧
ここでは、既に日本にいて、他のビザから特定技能への変更に必要書類一覧を紹介します。
改正が頻繁にありますので、申請の際は最新の情報を入管HPでご確認ください。
- 書類は日本語または日本語訳付きのもの(母国語での記載が必要な書類もあります。)
① 本人に関する書類
| 書類名 | 主な内容・備考 |
|---|---|
| 提出書類一覧表 | |
| 変更許可申請書 | 第30号様式 |
| 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 申請人の報酬に関すること等を参考様式に記載 |
| 特定技能雇用契約書 | 参考様式。申請人の署名と所属機関の印が必要 |
| 雇用条件書の写し、賃金の支払 | 就労内容、報酬、労働条件など参考様式に記載 |
| 雇用の経緯に係る説明書 | 参考様式。あっせんに関することを記載 |
| 健康診断個人票、受診者の申告書 | 参考様式を使用。 |
| 住民税の課税証明書、納税証明書 | 直近1年分 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 住民税の課税証明書が証明している対応年度 |
| 国民健康保険証の写し、保険料納付証明書 | 直近1年分 |
| 国民年金保険料納付証明書 | 申請日の前々月までの24か月分 |
| 公的義務履行に関する誓約書 | 参考様式。税金・社会保険料に滞納がある場合 |
| 1号特定技能外国人支援計画書 | |
| 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | 参考様式。登録支援機関に支援を全部委託する場合 |
| 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 | 対象国籍は、タイ・ベトナム・カンボジア |
| 在留カード | 両面コピー |
| パスポート | 顔写真ページ+スタンプ欄 |
| 顔写真(4×3cm) | 6ヶ月以内、無背景、無帽 |
| 履歴書/経歴書 | 学歴・職歴・試験履歴など記載 |
② 受入れ機関の適格性に関する書類
| 書類名 | 主な内容・備考 |
|---|---|
| 特定技能所属機関概要書 | 参考様式。役員、決算、従業員数等を記載 |
| 登記事項証明書 | 法人の履歴事項全部証明書 |
| 役員の住民票 | 本籍地記載あり、マイナンバー省略 |
| 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 参考様式 |
| 労働保険料納付証明書 | |
| 健康保険料・厚生年金保険料領収書 | |
| 納税証明書(その3) | 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税 ※税務署発行 |
| 法人住民税の納税証明書 | 直近1年分 ※市町村発行 |
| 決算報告書(損益計算書・貸借対照表) | 前3年度分 |
③ 分野に関する書類
| 技能試験合格証明書の写し | 技能評価試験の合格証明書のコピー |
| 日本語能力試験の合格証明書の写し | 日本語能力試験(N4)以上 |
| 協議会加入証明書(該当分野) | 申請前に各分野の協議会への加入が必要 |
| その他分野ごとの補助資料 | 例:外食→保健所長の営業許可証、建設→資格保有証 、宿泊→旅館業許可証 |
2025年4月1日改正の主なポイント
1. 提出書類の省略ルールの改正
Ⅰ.同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている場合
Ⅱ.下記①~⑥の機関については、過去3年間に指導勧告書の交付を受けておらず、在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行う場合
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人
「Ⅰ.」又は「Ⅱ.」の場合は、「本人に関する書類」の一部と、「受入れ機関の適正に関する書類」の全部を省略することができます。省略した書類は、定期届出のときに、一緒に提出することになります。ただし、「Ⅱ.」に該当する場合は、定期届出時の「受入れ機関の適正に関する書類」の提出も省略できます。
2. 定期届出の頻度と様式が変わる
これまでは3ヶ月ごとだった届出が、2026年4月以降「年1回」に統一されます 。
「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書が、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」の1枚でまとめる様式に統合され、対象年度(4/1〜翌3/31)の翌年4/1〜5/31までの提出が必要となります。
3. 地方自治体への協力確認書の提出
地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。また、地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。特定技能所属機関は、外国人の居住地および勤務先市区町村に「協力確認書」を提出します。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交
付申請又は在留資格変更許可申請を行う前に、提出します。
既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更
許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前の提出になります。
まとめ
日本国内で深刻化する人手不足の現実があり、とくに中小企業や地方では、若手労働力が年々減少し、「現場が回らない」「担い手がいない」という業種が急増しています。
特定技能とは「日本の現場で即戦力として働ける外国人材を受け入れるための制度」です。
したがって、これまでのように“実習生”としてではなく、「労働者」としての在留が制度的に認められることが最大の特徴です。しかも、特定技能2号に進めば、長期在留や家族との生活も可能になり、日本社会に根を張って働ける制度として、外国人にとっても魅力が大きいのです。
さらに、特定技能は単なる“労働力の補填”ではなく、日本社会が多文化共生へ向かうための制度的基盤でもあり、企業や自治体は、生活支援や言語教育などを通じて、外国人と地域社会の間に新しい信頼関係を築くことが今後求められます。
ビザ申請のことなら取次申請行政書士におまかせください

こんなお悩みありませんか?
●ビザ取得のやり方がわからない
●自分で申請したけど許可がおりなかった
●更新期限がせまってきて間に合うのか心配
●転職が決まったけど忙しくてビザ変更するひまがない

そのお悩み行政書士にお任せください
当事務所では、申請取次行政書士が責任をもって申請書類の作成を行いますので、安心してお任せください。ご依頼を受けたあとは、必要書類をご案内いたします。書類のチェック・入国管理局への申請書類の提出は、当事務所で代行しますので、お客様のご負担はありません。
お問合せフォームは、こちらから
お問い合わせフォームからのご相談は、24時間いつでも受付中。
しまだ行政書士事務所090-3599-0809初回相談無料。お気軽にお問い合わせください。電話に出れないときは折返しお電話致します。
メールでのお問い合わせはこちら 24時間いつでも受付中!